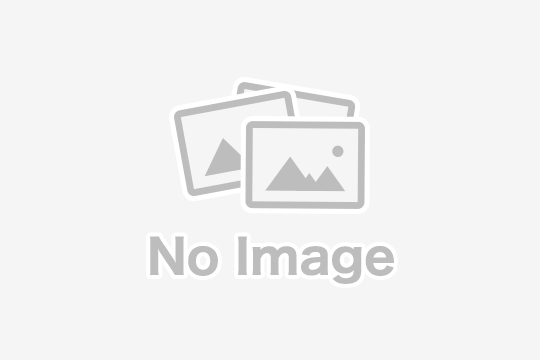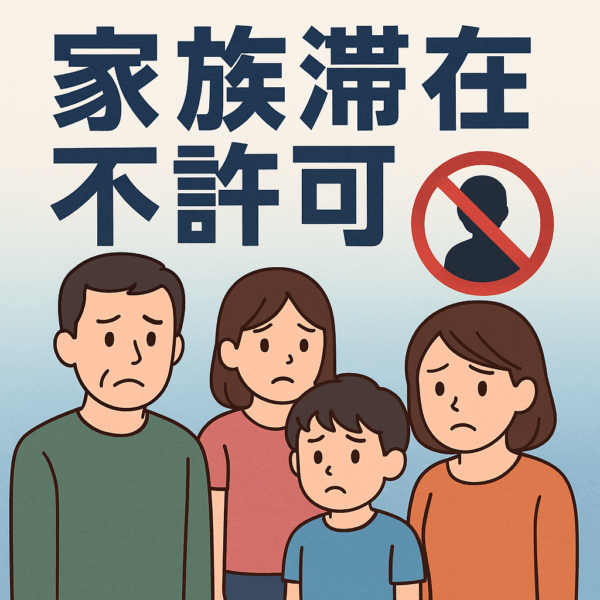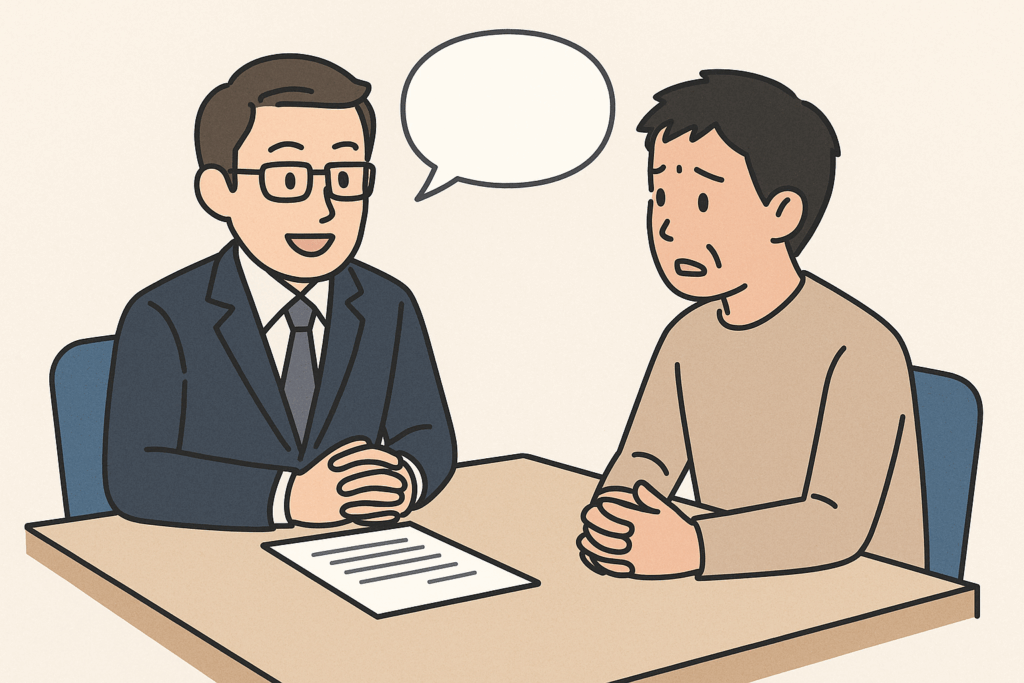
「入管に呼び出された」「家族が収容されるかもしれない」―― そんなとき、どう対応すべきか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「収容」「仮放免」「仮滞在」など、入管手続きに関わる用語や流れをやさしく解説します。
また、行政書士がどの段階で支援できるのか、実務の視点でお伝えします。
なお、退去強制手続きの流れについては、下記の記事でわかりやすくまとめています。
収容とは?
「収容」とは、退去強制の対象となる外国人を入国管理局が身柄を拘束し、収容施設(入管センターなど)に留め置く措置を指します。
入管法に基づき、以下のような理由で収容されることがあります。
- 不法残留や不法入国が判明した場合
- 退去強制手続き中に逃亡の恐れがあると判断された場合
- 過去に収容歴がある、または危険性があると判断された場合
収容された場合、家族との面会や医療へのアクセスなど生活面でも制限が大きく、精神的・経済的な負担が生じます。
仮放免とは?
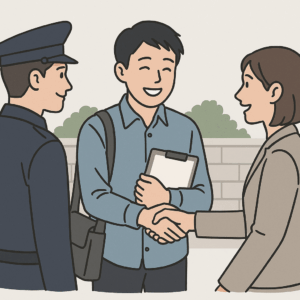
「仮放免(かりほうめん)」とは、収容された外国人について、一定の条件のもと一時的に収容を解く制度です。
仮放免が認められると、収容施設の外で生活することが可能になります。
ただし…
- 就労はできない
- 定期的な出頭義務がある
- 引越しや外泊にも制限がある
また、仮放免の許可はあくまで一時的な措置であり、最終的に退去強制手続きが終結するまで在留資格が与えられるわけではありません。
仮放免の申請には、身元保証人や保証金が必要となることが多く、準備に時間を要することもあります。
仮放免の審査では、逃亡の恐れがないか、生活基盤があるか、身元保証人の有無などが考慮され、総合的に判断されます。
仮放免の申請には、身元保証人や保証金が必要となることが多く、準備に時間を要することもあります。
仮放免の審査では、逃亡の恐れがないか、生活基盤があるか、身元保証人の有無などが考慮され、総合的に判断されます。
なお、仮放免中は原則として就労できませんが、退去強制令書がまだ発付されていない段階で、生活維持が困難な場合などには、例外的に報酬を受ける活動が認められることもあります(法務省 監理措置に関する各種申請ページ 参照)。
こうした活動は、あくまで入管の判断に基づく例外的な措置であり、事前に個別の相談が必要です。
監理措置制度の全体像については、法務省 監理措置制度ページやQ&Aもご参照ください。
行政書士ができること・できないこと
行政書士が対応できるのは、原則として「退去強制手続き前の段階」に限られます。つまり、収容が決定され、実際に収容された後は、行政書士ができる支援は非常に限られます。
仮放免の申請書作成や、本人や家族の生活状況などを説明する資料の作成については、行政書士でも対応可能な場合があります。
なお、仮放免の審査や収容後の対応において、法律上の争いに発展するような場面では、行政書士の対応範囲を超えることがあります。
収容される前にできること
入管からの呼び出しがあった段階で、すでに「収容の可能性がある」ということを意味します。
この段階で、生活状況や家族関係、就労実態などを整理し、在留特別許可の可能性を探る資料を整えることで、収容や退去を回避できる可能性があります。
行政書士はこの段階で、理由書の作成や証拠資料の準備、相談対応などで力になることができます。
「まだ収容されていない」段階で、何ができるかを整理し、早めに対応することが非常に重要です。
まとめ
収容の前に、できることがあります。
入管に呼び出された時点で、手続きはすでに進んでいます。 行政書士が支援できるのは「退去令が出る前」「収容される前」の段階です。
「うちの外国人スタッフが収容されるかもしれない」「家族が呼び出された」といった状況に直面したら、 早めに専門家に相談することが大切です。
状況に応じて、資料の整備や仮放免の申請、在留特別許可の準備など、できる支援をご提案いたします。
行政書士は法律の手続きだけでなく、不安な思いに寄り添う立場としてお力になります。
ご相談はお気軽にどうぞ
私たち行政書士は、あくまで法令に則った手続きの中で、支援できることを丁寧にご案内しています。
無理な理由づけで滞在を引き延ばすことを目的とするものではありません。
制度の趣旨を踏まえた上で、できる準備と判断をご一緒に考えていけたらと思います。
どうぞ、安心してご相談ください。