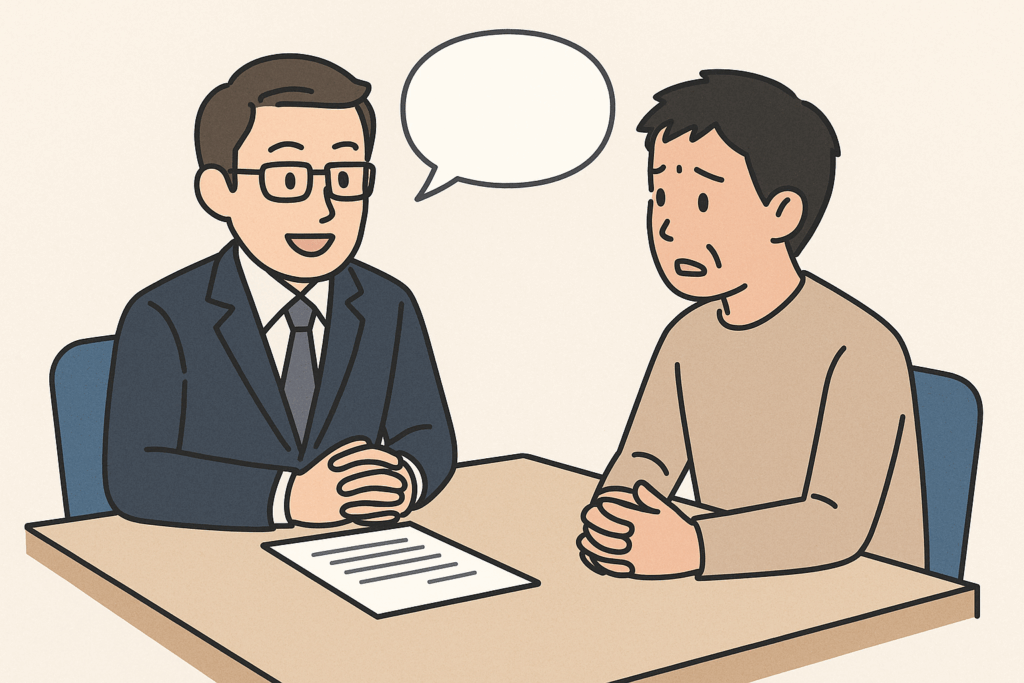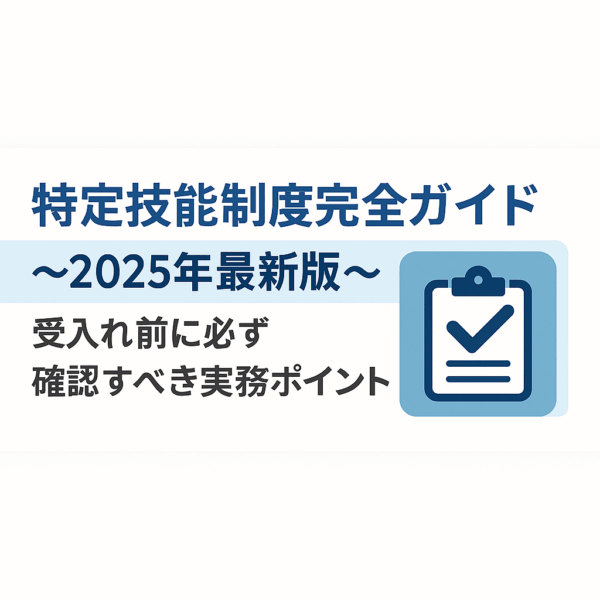
この記事のポイント
- 特定技能制度の最新変更点(2025年4月施行)を実務視点で解説
- 受入れ前に確認すべきチェックポイントを網羅
- 見落としやすい注意点と対策を具体的に紹介
特定技能制度は2019年の開始以来、制度改正が頻繁に行われており、2025年4月にも大幅な運用変更が実施されました。外国人材の受入れを検討されている企業の皆様にとって、制度の正確な理解と適切な準備が成功の鍵となります。
本記事では、特定技能外国人の受入れを検討されている企業の皆様が、制度を正しく理解し、適切な準備を進められるよう、実務に直結するポイントを分かりやすく解説いたします。不明な点がございましたら、専門家にお気軽にご相談ください。

〜制度理解と適切な準備が成功への第一歩〜
特定技能制度の基本構造【2025年最新版】
特定技能制度は、人手不足が深刻な16分野で外国人材を受入れる制度です。2024年3月に4分野が新たに追加され、現在は以下の分野で受入れが可能です。
特定技能対象分野(全16分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- NEW 自動車運送業
- NEW 鉄道
- NEW 林業
- NEW 木材産業
※詳細は出入国在留管理庁「特定技能制度」をご参照ください
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号
- 在留期間:最長5年(1年・6か月・4か月ごとの更新)
- 家族帯同:不可
- 支援計画の実施が義務(10項目)
- 技能試験・日本語試験合格、または技能実習2号を良好に修了が要件
特定技能2号
- 在留期間:無期限(更新制)
- 家族帯同:可能(配偶者・子)
- 支援計画の実施義務なし
- 移行可能な分野:11分野(介護を除く)
2025年4月からの重要な制度変更
⚠️ 必ず対応が必要な変更点
2025年4月1日から施行された省令改正により、以下の対応が新たに必要となりました。これらは法的義務ですので、必ず対応してください。
※詳細は出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」をご確認ください
協力確認書の提出義務【NEW】
特定技能外国人を受入れる企業は、外国人が活動する事業所の所在地および住居地の市区町村に対して「協力確認書」の提出が義務付けられました。
提出タイミング
- 初回受入れ:雇用契約締結後、在留資格申請前
- 既存受入れ:2025年4月1日以降の初回更新申請前
提出先
- 事業所所在地の市区町村
- 外国人の住居地の市区町村
- ※同一市区町村の場合は1通のみ
※協力確認書の詳細は出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご参照ください
随時届出の変更【NEW】
新たに届出が必要となる事項
- 在留資格許可後1か月経過しても就労開始していない場合
- 雇用後1か月以上活動できない事情が生じた場合
届出が不要となった事項
- 外国人の自己都合退職時の「受入れ困難」届出
- ※ただし、雇用契約終了届出は引き続き必要
定期届出の大幅変更【NEW】
- 提出頻度:四半期ごと → 年1回
- 初回提出:2026年4月〜5月(2025年度分)
- ※2026年4月まで定期届出の提出は不要
- ※2025年度分の定期届出は従来通り2025年4月15日まで要提出

〜新制度に対応した適切な書類準備が重要〜
受入れ前に確認すべき7つのチェックポイント
対象分野・業務の確認
まず、自社の業務が特定技能の対象分野に該当するかを正確に確認しましょう。分野の境界が曖昧な業種(例:飲食店が外食業か宿泊業か)については、各分野のジョブディスクリプション(職務記述書)で詳細を確認することが重要です。
確認方法
- 出入国在留管理庁の分野別運用方針を確認
- 各分野のジョブディスクリプションで業務内容を照合
- 不明な場合は管轄の出入国在留管理局に事前相談
※分野別運用方針は出入国在留管理庁HPの「分野別運用方針・分野別運用要領」からご確認いただけます
外国人の資格要件確認
特定技能外国人には以下の要件があります。技能実習からの移行時期にも注意が必要です。
基本要件
- 18歳以上
- 技能試験合格 + 日本語試験合格(N4相当以上)
- または技能実習2号を良好に修了(分野一致の場合は試験免除)
注意事項
- 技能実習からの移行は実習終了前1年以内に申請
- 在留資格の空白期間が生じないよう計画的に手続き
労働条件の整備
必須要件
- 日本人と同等以上の報酬
- 社会保険・雇用保険の完備
- 適切な雇用契約書・労働条件通知書の作成
- 労働関係法令の遵守
支援体制の構築(特定技能1号のみ)
特定技能1号外国人には法定の10項目支援が義務付けられています。自社対応か登録支援機関への委託かを検討しましょう。
法定支援10項目(主要なもの)
- 生活オリエンテーション
- 住宅確保・生活に必要な契約支援
- 公的手続き同行支援
- 日本語学習支援
- 定期面談(3か月に1回以上)
- 苦情・相談対応
2025年4月からの変更点
- 定期面談でオンライン実施が可能に
- 支援計画作成時に自治体の共生施策を考慮
協力確認書の準備【NEW】
準備すべきこと
- 事業所所在地の市区町村の提出方法を確認
- 外国人の住居予定地の市区町村の提出方法を確認
- 協力確認書の様式をダウンロード・記入
- 提出期限の確認(在留資格申請前まで)
登録支援機関の選定(外部委託の場合)
選定ポイント
- 法務省認定の登録支援機関であることを確認
- 対象分野での支援実績があるか
- 支援内容と費用の明確化
- 緊急時の対応体制
※登録支援機関一覧は出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」でご確認いただけます
継続的な制度理解と更新準備
重要な考慮事項
- 在留期間更新は原則1年ごと
- 特定技能2号への移行可能性(該当分野のみ)
- 転職は可能(他の受入れ機関での就労)
- 制度変更への対応準備

〜適切な準備により円滑な手続きが可能〜
実務で見落としやすい注意点
❗ よくある失敗パターン
1. 分野判定の誤り
例:介護施設での調理業務 → 介護分野ではなく飲食料品製造業分野の可能性
2. 技能実習からの移行タイミング
技能実習修了直前の申請では在留資格の空白期間が発生するリスク
3. 協力確認書の未提出NEW
2025年4月以降、未提出では在留資格申請ができません
4. 支援計画の形式的対応
外国人の実情に合わない支援計画では定着率が低下
成功のためのポイント
- 制度理解を深めるため、定期的な情報収集を心がける
- 外国人本人への制度説明を丁寧に行う(母国語資料の活用)
- 行政書士等の専門家との連携を検討
- 社内の受入れ体制整備と理解促進
- 地域の国際交流協会等との連携
分野別の特記事項【2025年最新情報】
介護分野
- 受入れ法人は協議会への入会証明書が必要
- 2025年より訪問系サービスでの就労が可能に
- 身体介護・支援業務が中心
外食業分野
- 試験は国内外でCBT方式で実施
- 週30時間以上、週5日以上の雇用条件
- 2025年5月に基準改正実施
新規追加分野(2024年〜)
- 自動車運送業:日本の運転免許取得が前提条件
- 鉄道:運輸係員業務はN3以上の日本語能力が必要
- 林業・木材産業:安全管理に特に注意
工業製品製造業分野
- 2025年5月に要領改正
- 繊維工業では勤怠管理の電子化が追加要件
- 特定技能2号への移行が可能(一部業務区分)
まとめ
特定技能制度成功の3つのポイント
- 制度の正確な理解:2025年4月の変更点を含めた最新情報の把握
- 計画的な準備:協力確認書提出など新たな義務への対応
- 継続的なサポート:外国人材の定着に向けた支援体制の構築
特定技能制度は人手不足解消の有効な手段ですが、適切な理解と準備なしには成功できません。制度が複雑で不安に感じられる場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
外国人材の受入れは、単なる労働力確保ではなく、地域社会との共生を目指す取り組みです。企業として責任を持って対応し、外国人材が安心して働ける環境づくりに努めることが、長期的な成功につながります。