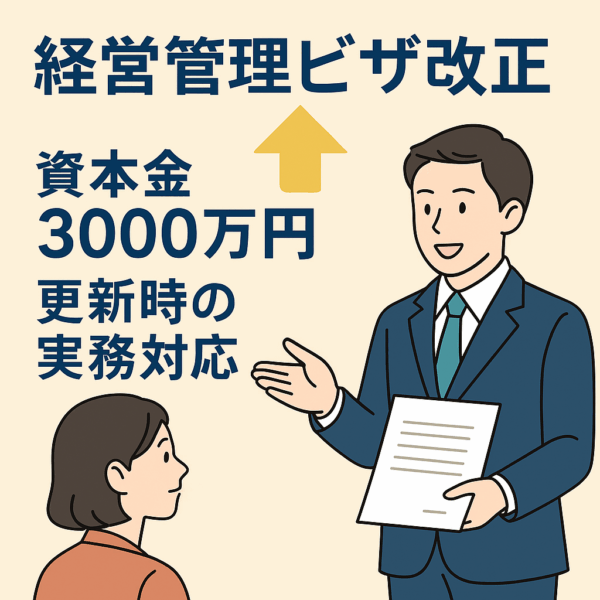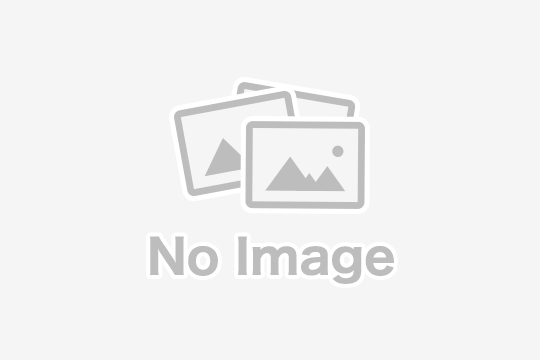日本の労働市場において、外国人労働者の受け入れは重要な課題となっています。特に、少子高齢化が進む中で、労働力不足を補うための制度が求められています。そこで登場したのが「育成就労制度」です。本記事では、育成就労制度の大枠と、技能実習制度との違いについて詳しく解説します。
育成就労制度の大枠
育成就労制度は、日本の産業発展のために外国人材を育成・確保することを目的としています。この制度では、外国人が3年間の育成期間を通じて必要なスキルを習得し、特定技能1号の水準に到達することを目指します
1. 目的
育成就労制度の主な目的は、以下の通りです。
- 人材育成
外国人労働者に対して、日本で必要とされる技能や知識を習得させること。 - 人材確保
労働力不足が深刻な分野において、即戦力となる人材を確保すること。 - キャリアアップの道筋を明確化
労働者の権利を適切に保護し、関係機関の要件等を適正化。
このように、育成就労制度は外国人労働者のスキル向上と労働力不足の解消を目指し、さらに労働者の権利保護とキャリアアップの支援を通じて、日本の魅力を高めることを目的としています。
2. 対象職種
現時点では、育成就労制度の受け入れ対象分野は特定技能制度と原則として一致しています。ただし、特定技能の受け入れ対象分野であっても、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外となります。例えば、特定の専門技術が必要な分野や、短期間での技能習得が難しい分野などが該当します。
育成就労制度の受け入れ対象分野である育成就労産業分野については、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に決定されることとなります。
このように、育成就労制度は特定技能制度と連携しつつ、実際の育成が効果的に行える分野に限定されています。
3. 日本語能力
育成就労制度では、就労開始時点での日本語能力に関する要件が設定されています。
- 日本語能力A1相当以上(JLPTのN5など)の試験合格
- それに相当する日本語講習の受講
4. 在留期間
育成就労制度の在留期間は基本的に3年間です。この期間中に必要な技能を習得し、特定技能1号への移行を目指します。特定技能1号の在留期間は最大5年間であり、特定技能2号に移行した場合は在留期間に制限がありません。
このように、育成就労制度は段階的なスキルアップと長期的な在留を可能にする仕組みになっています。
技能実習制度との違い
育成就労制度と技能実習制度は、外国人労働者の受け入れを目的としていますが、その目的や運用方法にはいくつかの違いがあります。
1. 目的の違い
- 技能実習制度
国際貢献を目的とし、開発途上国等の外国人に対して日本の技能を移転することを目指しています。 - 育成就労制度
日本国内の人材不足を補うために、即戦力となる人材を育成・確保することを目的としています。
2. 対象職種の違い
- 技能実習制度
単純労働は不可。90職種165作業と幅広い職種で受け入れが可能。 - 育成就労制度
特定技能制度と原則一致
3. 在留期間の違い
- 技能実習制度
最大5年間の在留が認められています。 - 育成就労制度
基本的に3年間の在留期間が設定されています。
4. 転職・転籍の可否
- 技能実習制度
原則として転職・転籍は認められていません。 - 育成就労制度
同一企業で1年以上就労した後、一定の条件を満たせば転職・転籍が可能です。
5. 日本語能力要件
- 技能実習制度
日本語能力について特に規定はありません。(介護のみN4合格) - 育成就労制度
原則N5程度。またはそれに相当する日本語講習の受講
技能実習制度の現実と課題
技能実習制度は、その建前と現実の間に大きな乖離があることが指摘されています。技能実習制度の本来の目的は、発展途上国の若者に日本の優れた技能や技術を学んでもらい、母国の発展に寄与することです。
しかし、実際には以下のような問題が存在します。
1. 技術習得の実態
多くの技能実習生は、特定の製品の特定の作業を繰り返すだけで、幅広い技術や知識を習得する機会が限られています。例えば、ある縫製工場では、技能実習生がタオルしか作っていないのに、「婦人服や靴下も作っている」と虚偽の報告をするよう指示されていたケースもあります。
2. 労働環境の問題
技能実習生は、長時間労働や賃金未払いといった労働環境の問題に直面することが多いです。また、技能実習生の日本語能力が不十分であり、意思疎通が困難なケースもあります。
3. 借金問題
来日前に高額な借金を背負って日本に来ることもあるようです。このため、実習生は経済的なプレッシャーにさらされることが多く、労働条件が悪くても我慢せざるを得ない状況に陥ることがあります。
育成就労制度のメリットとデメリット
育成就労制度には、企業、外国人労働者、そして日本社会にとって多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
メリット
- 企業にとってのメリット: 労働力不足に悩む企業が必要な労働力を確保しやすくなります。また、外国人労働者の日本語能力向上や技能習得を支援する仕組みが整っているため、即戦力となる人材を育成できます。
- 外国人労働者にとってのメリット: 日本語教育と技能習得の機会が提供されるため、日本での生活の質が向上し、将来のキャリアアップにもつながります。
- 日本社会にとってのメリット: 深刻化する人手不足の問題が緩和され、多文化共生社会の実現に寄与します。
デメリット
- 企業側の負担
外国人労働者の受け入れに伴う手続きやサポート体制の整備が必要です。 - 外国人労働者の保護
労働条件や人権の保護が十分に行われない場合、問題が発生する可能性があります。 - 人材の集中
転勤が可能なため、条件の良い企業に人材が集中し、人手不足の問題が解消されない可能性があります。 - 文化・言語の壁
外国人労働者と日本人労働者の間で文化や言語の違いが障壁となり、コミュニケーションの問題が発生することがあります。これにより、職場での協力や効率が低下する可能性があります。 - 教育・研修のコスト
外国人労働者に対する日本語教育や技能研修のコストが企業にとって負担となることがあります。特に中小企業にとっては、この負担が大きくなる可能性があります。 - 社会的な受け入れ
外国人労働者の増加に伴い、地域社会での受け入れ態勢や多文化共生の意識が求められます。これが十分に整っていない場合、地域社会での摩擦や誤解が生じることがあります。 - 監理団体の負担
監理団体も外部監査人の設置が義務付けられるため、監査体制の整備や運営コストが増加する可能性があります。
このように、育成就労制度には多くのメリットがある一方で、企業や社会全体にとっての課題も存在します。
これらのデメリットを克服するためには、制度の適切な運用と改善が必要です。
まとめ
育成就労制度は、日本の労働市場において重要な役割を果たす制度です。技能実習制度との違いを理解し、適切に運用することで、企業、外国人労働者、そして日本社会全体にとって多くのメリットを享受できるでしょう。今後も制度の改善や運用の見直しが求められる中で、育成就労制度の活用がますます重要となることが期待されます。
この記事が、育成就労制度についての理解を深める一助となり、皆様のお役に立てれば幸いです。