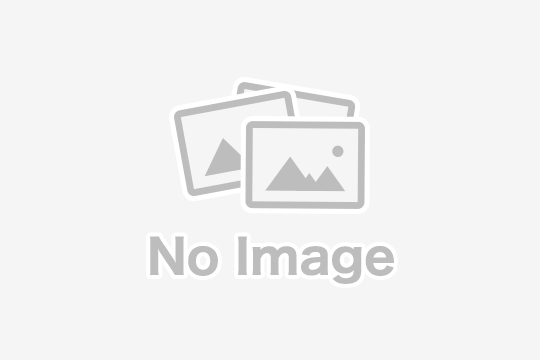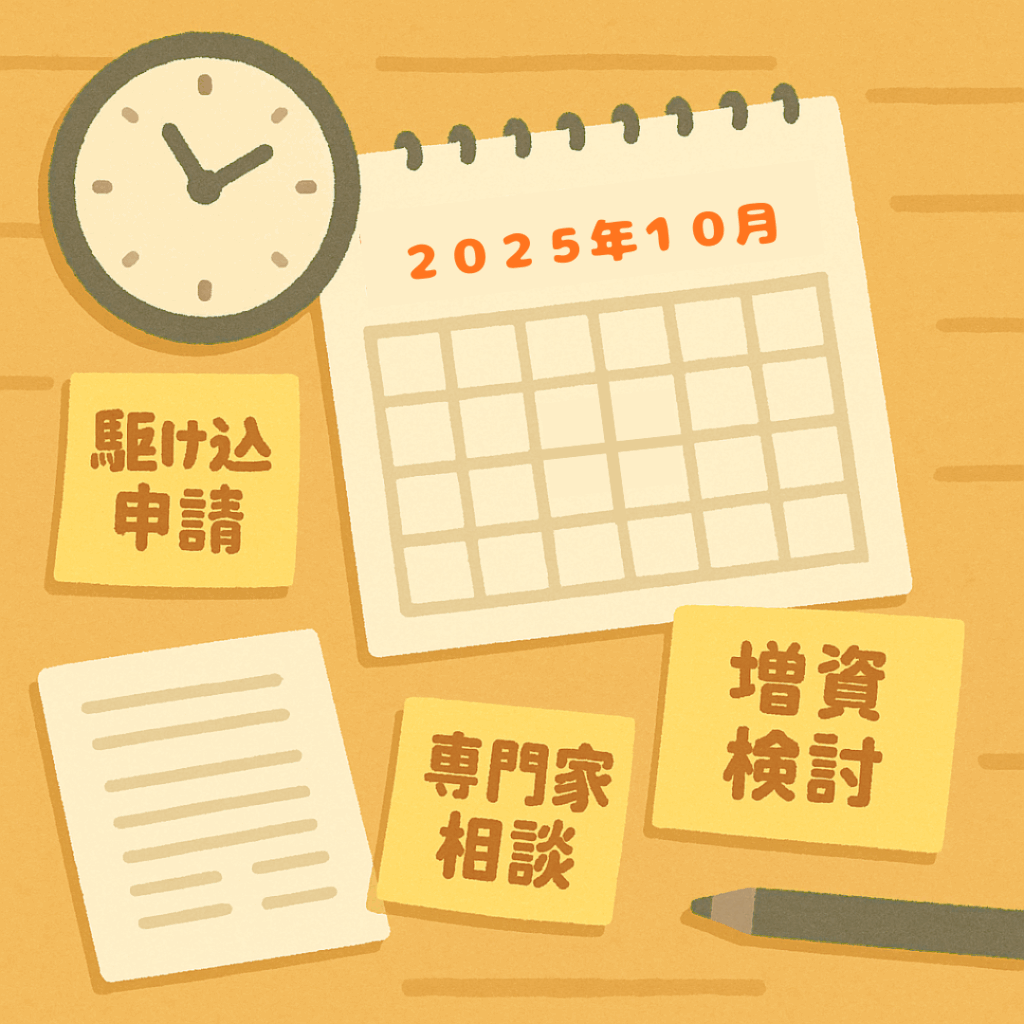前回のブログでは、強制退去手続きの基本的な流れについて説明しました。今回は、その中でも特に重要な「監理措置制度」について詳しく解説します。この制度は、在留資格を持たない外国人が強制退去手続き中にどのように生活し、どのような活動が許されるのかを規定しています。
報酬を受ける活動の許可について
まず、在留資格がない外国人は原則として就労が認められていません。しかし、退去強制令書が発布される前の被監理者に限り、例外的に報酬を受ける活動に従事することが許される場合があります。
許可の要件
報酬を受ける活動が許可されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 退去強制令書発付前の被監理者からの申請であること
退去強制令書が発布される前に、被監理者自身が申請を行う必要があります。 - 監理者の同意があること
申請を行う際には、監理者の同意が必要です。監理者は被監理者の生活を監督する役割を担います。 - 主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づく活動であること
被監理者が従事しようとする活動は、主任審査官が指定する日本国内の公私の機関との雇用契約に基づくものでなければなりません。 - 活動が生計の維持に必要な範囲内であること
報酬額は生計の維持に必要な範囲内であることが求められます。 - 活動が相当と認められること
当該活動が適切であると認められる必要があります。 - 監理人による監理の下で行われること
活動は監理人の監理の下で行われる必要があります。
監理措置決定通知書に記載される内容
監理措置決定通知書には、以下の内容が記載されます。
- 勤務地
日本国内の公私の機関が指定されます。 - 活動内容
被監理者が従事する具体的な活動内容が記載されます。 - 報酬額の上限
生計維持に必要な範囲内での報酬額が設定され、個別の事案ごとに判断されます。 - その他条件
その他、必要な条件が記載されます。
自ら事業を運営する活動は不可
被監理者が自ら事業を運営する活動は、報酬を受ける活動として認められません。
許可を受けずに報酬を受ける活動を行った場合の罰則
許可を受けずに報酬を受ける活動を行った場合、3年以下の懲役もしくは禁固、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、懲役もしくは禁固と罰金の併科も規定されています。
退去強制令書の発付前か後かの確認方法
退去強制令書の発付前か後かは、監理措置決定通知書に就労の禁止の記載があるかどうかで判断できます。
監理人の要件
監理人には以下の要件があります。
- 監理人の責務を理解していること
監理人はその責務を十分に理解している必要があります。 - 監理措置決定を受けようとする外国人の監理人になることを承諾していること
監理人は、被監理者の監理人になることを承諾している必要があります。 - 任務遂行能力を考慮して適当と認められること
監理人は、任務を遂行する能力があると認められる必要があります。典型的には、本人の親族や知人などが想定されますが、これに限りません。行政書士、弁護士、支援者、登録支援機関の職員なども含まれます。
監理人の責務
監理人には以下の責務があります。
- 被監理者の生活状況の把握、指導・監督
被監理者の生活状況を把握し、適切な指導・監督を行います。 - 相談に応じ、援助を行う
被監理者からの相談に応じ、必要な援助を行います。 - 届出自由が発生したときの届出
届出自由が発生した場合には、速やかに届出を行います。 - 主任審査官からの報告要求に応じる
主任審査官から報告を求められた場合には、適切に報告を行います。
定期的な連絡と指導・監督
監理人は定期的に被監理者と連絡を取り、条件や届出義務を守っているか確認します。また、必要な指導・監督を行い、被監理者が適切に生活できるよう支援します。ただし、常時生活状況を把握する過度な負担は求められません。
届出の期限
届出は7日以内に行う必要があります。監理者は定期的な届出は必要なく、届出事由が発生した場合のみ届出を行います。一方、被監理者は3か月を超えない範囲内で定期的に届出を行う必要があります。
届出をしない場合の罰則
届出をしない、または虚偽の届出を行った場合、監理人の選定が取り消されることや処罰を受けることがあります。
届出事由
以下の場合には届出が必要です。
- 被監理者が特定の監理措置決定の取り消し事由に該当することを知ったとき
- 被監理者が死亡したとき
- 監理者と被監理者との間の親族関係が終了したとき
- 監理者と被監理者の間の雇用関係が終了したとき
- 主任審査官が管理措置を継続することに支障があると判断したとき
監理人の承諾書兼誓約書の提出
監理措置決定を受けようとする外国人の監理人となることを承諾している場合、監理人承諾書兼誓約書を提出する必要があります。
監理人の要件
監理人の要件には以下の項目が含まれます。
- 年齢、職業、収入、資産、素行
- 外国人との関係
- 金銭の支払いの相当性
未成年や精神機能障害により必要な認知、判断、意思疎通が適切に行えない者、在留資格を有していない外国人は監理人として認められません。
監理人の辞任
監理人が辞任する場合、主任審査官に届け出る必要があります。辞任しようとする日の30日前までに理由や辞任する年月日を地方出入国在留管理官署に届け出るよう努めてください。
監理人が責務を果たさなかった場合の罰則
監理人が責務を果たさなかった場合、監理人の選定が取り消されることがあります。また、入管法第77条の2各号に該当する場合、10万円以下の科料が科されることがあります。
監理措置決定申請の手続き
監理措置決定申請は地方出入国在留管理官署に提出します。必要書類は各種揃えて提出する必要があります。
報酬を受ける場合の必要書類
報酬を受ける活動を行うためには、以下の書類を提出する必要があります。
- 申請書
被監理者が報酬を受ける活動を行うための申請書です。 - 雇用契約書
主任審査官が指定する機関との雇用契約書が必要です。 - 監理人の同意書
監理人が申請に同意していることを示す同意書です。 - その他必要書類
その他、必要に応じて追加の書類が求められることがあります。
指定住居変更申請
被監理者が住居を変更する場合、指定住居変更申請を行う必要があります。この申請は、地方出入国在留管理官署に提出します。
行動範囲拡大許可申請
被監理者が行動範囲を拡大する必要がある場合、行動範囲拡大許可申請を行います。この申請も地方出入国在留管理官署に提出します。
まとめ
強制退去手続きにおける監理措置制度は、在留資格を持たない外国人が適切に生活し、必要な活動を行うための重要な制度です。監理人の役割や責務、報酬を受ける活動の許可要件など、細かい規定が設けられており、これらを遵守することが求められます。
監理人としての責務を果たし、被監理者が適切に生活できるよう支援することが重要です。また、必要な届出や申請を適切に行うことで、法令を遵守しながら生活を続けることができます。
この記事が、監理措置制度についての理解を深める一助となれば幸いです。