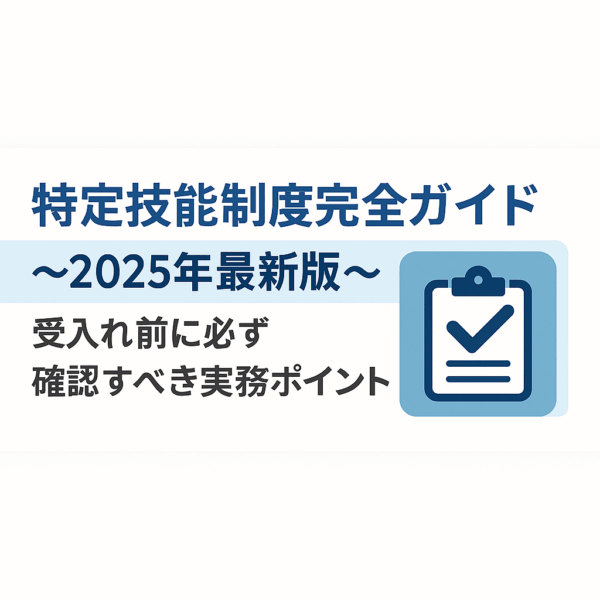日本の技能実習制度は、外国人労働者が日本で技能を習得し、母国に帰国後にその技能を活かして発展に寄与することを目的としています。近年、新たに育成就労制度が導入される予定ですが、技能実習制度は依然として重要な役割を果たしています。本記事では、技能実習制度の運営において監理団体が果たすべき役割と、定期監査の重要性について詳しく解説します。
監理団体の役割
監理団体は、技能実習生が適切な環境で実習を行い、法令を遵守しているかを監督する重要な役割を担っています。具体的には、以下のような監理項目があります。
実地確認
・実習実施者の現場を訪問し、実習の状況を確認
・実習責任者や指導員からの報告を受け、実習の進捗状況を把握
面談の実施
・実習実施者が技能実習生の4分の1以上と面談を行い、実習の状況や問題点を確認
面談は現地で行うことが望ましいですが、現場絵の立ち入りが難しい場合は特記事項を記載し、実習現場近くでの面談を行うなどの工夫が必要です。
設備・帳簿書類の確認
・実習計画に記載された機械器具の設置状況や、安全衛生の配慮がなされているかを確認
・賃金台帳やタイムカードを確認し、適切な報酬と労働時間が守られているかをチェック
宿泊施設・生活環境の確認
・実習生が快適に生活できる環境が整っているかを確認
定期監査の重要性
監理団体は、3か月に一度以上の定期監査を行うことが求められています。定期監査では、以下のポイントを重点的に確認します。
割増賃金の不払い
・実習生に対して適切な割増賃金が支払われているかを確認
労働時間の偽装
・実習生の労働時間が適切に記録されているか、偽装がないかをチェック
技能実習計画とは異なる作業への従事
・実習生が技能実習計画に沿った作業を行っているかを確認
実習実施者以外の事業所での作業従事
・実習生が他の事業所で作業を行っていないかを確認
不法就労者の雇用
・実習生が不法就労者として雇用されていないかを確認
入国後講習期間中の業務への従事
・実習生が入国後の講習期間中に業務に従事していないかを確認
面談の方法
面談は口頭で行うこともできますが、質問表などを作成して実施する方法もあります。個別面談や集団面談のいずれも可能です。面談の際には、実習生の意見や問題点をしっかりと聞き取り、適切な対応を行うことが重要です。
設備・帳簿の確認
設備や帳簿の確認では、以下の点に注意します。
機械器具の設置
・実習計画に記載された機械器具が適切に設置されているかを確認
安全衛生の配慮
・実習生の安全を確保するための措置が講じられているかを確認
計画通りの実習
・実習計画に沿った実習が行われているかを確認
賃金台帳・タイムカードの確認
・賃金台帳やタイムカードを確認し、適切な報酬と労働時間が守られているかをチェック
業務内容・指導内容の日誌
・実習生の日誌を確認し、計画通りの実習が行われているかを確認
臨時監査
定期監査のほかにも、実習実施者が実習認定の取消事由に該当する疑いがある場合や、不法就労者の雇用など出入国管理関係法令に違反している疑いのある情報を得たときには、直ちに臨時の監査を行う必要があります。
外部監査人の導入
定期監査や臨時監査において実習実施者の違反が発覚した場合、場合によっては、外国人技能実習機構又は労働基準監督署に通報するという義務があります。
しかし、ここで関係性の影響が問題となることがあります。長期間の付き合いや関係性がある場合、違反が見つかっても適切な対応が取りにくいことがあります。こうした関係性を気にして監査の公正性が損なわれることが起きてはいけません。
このような問題を解決するためには、外部監査人を導入することが有効です。外部監査人は、第三者の立場から厳しい目で監査を行い、厳しい意見を述べることができます。違反を放置した場合、実習実施者だけではなく監理団体にも厳しい処分がある技能実習制度において、適切に処置する必要があります。
外部監査人の導入により、監理団体や実習実施者との関係性に左右されることなく、公正な監査が行われることが期待されます。これにより、実習生の権利が守られ、技能実習制度の適切な運営が確保されるでしょう。
まとめ
技能実習制度の運営において、監理団体の役割は非常に重要です。定期監査や臨時監査を通じて、実習生が適切な環境で実習を行い、法令を遵守しているかを確認することが求められます。監理団体は、実習実施者と連携しながら、技能実習制度の健全な運営を支える役割を果たしていく必要があります。また、外部監査人の導入により、より公正な監査が行われ、実習生の権利が守られることが期待されます。
この記事が技能実習制度についての理解を深める一助となれば幸いです。